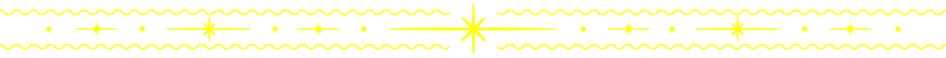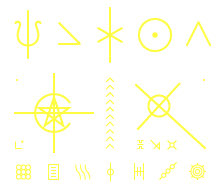少し前に書いてた「人間の知性の働きについて」の話の続きになります。
ここでは、人間や生物が「わかる」ことと、「わからない」ことの知的な境界について、考えてみたいと思います。
1、客観的に見ると、人間が知的に「わかる」ということは、同時にたくさんの知的に「わからない」状態をよしとしているようなところがある
まず最初に、ここでは、みなさんにとても身近な「水」を例にして考えてみたいと思うのですが、たいてい、小さな子供が「水」について理解してゆく際には、そうした子供にとって、非常に身近な簡単な内容、例えば、「水」というのは、水道や井戸から出てくる、透き通った冷たいピチャピチャしたものであるとか、川を流れているキラキラ光るものであるとか、時々、空からたくさん落ちてくる、プチョプチョした玉のようなものであるなどというように理解してゆくのではないか、と思われます。
つまり、小さな子供が「水」について理解してゆく際には、よく学校で学ぶような「水の融点は0度で、沸点は100度で、分子記号はH2Oである」というような科学的な定義や、様々な専門分野で使われる「水」に関する、かなり特殊な専門的な内容のようなものはいっさい除いて、そうした「水」についての、ごくごく一部の具体的な特徴や性質を知るだけで、そうした物事について、「わかった」と考えていることが多いということなのです。
つまり、どんな人であっても、人間的、あるいは、生物的な知性には限界があるので(これは機械やコンピューターであっても、ほぼ同じだと思いますが・・・)、いきなり非常に莫大な内容の理解は、なかなか難しい、というか、最初から、ほぼ完全に不可能なところがあるので、たいていは、どんな人であっても、そうした物事について、まずは、その人自身がわかることのできるようなレベルの内容を、少しずつ理解してゆくことしかできないようなところがあるのです。
そうすると、これはとても不思議な話になるのですが、多くの人々が、何らかの物事を「わかってゆく」際には、ひょっとしたら、ものすごく膨大な量の「わからない」ものがあるのかもしれないということと、それから、そもそも人間や生物が、そうした「わかる」という認識を積み重ねてゆくためには、その時々の「わかる」という認識のために、より複雑でややこしい内容や、また、その時のニーズにあまり関係ない内容に関しては、あえて「わからない」状態をよしとしている、さらにもっとはっきり言うと、そうした内容に対しては、そもそも、わかろうともしていない、というような少し不思議な知的矛盾のようなものを抱えた状態になりがちであるということが言えるようです(参考)。
Cecye(セスィエ)