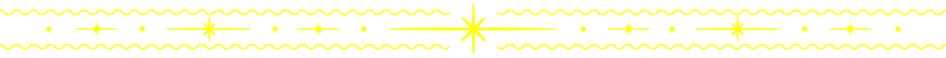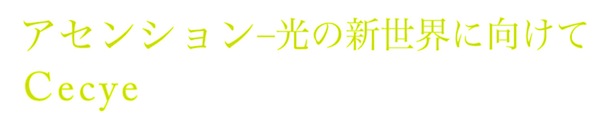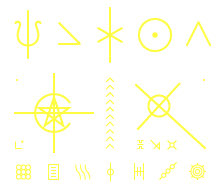2025年も、今日で最後の一日になりました。
みなさんは、今年はどんな一年になりましたか?
私は、20数年ぶりに入院レベルの病気にかかったので、以後、それを教訓にして、自分の健康習慣などをかなり大きく見直すことにしました。
私は、病気などに関しては、自分自身のこの世的なノウハウや霊的な能力でかなり防げたり、治したりできるという自信があったのですが、今回は、それでもうまく上手に防げなかったところがあったので(自分でできる範囲で治しはしました)、現在、自分の健康習慣などを、いろいろ試行錯誤しながら変更するようにしていっています。
このブログでは、霊的な内容に関しては、以前にかなりたくさん載せているで、私としては、最近はそうした霊的な情報を、それ以上細かく載せる必要性は、あまり感じていません。
また、そうした霊的な情報は、他にもたくさん発表してくれている人がいるようなので、それゆえ私としては、霊的な内容であっても、もっとマクロの観点から見た霊的な情報について(書く際には、結構、かなり長かったり、専門的だったりして、非常に面倒臭かったりするのですが・・・)、載せることが、最近は多くなってきているように感じております
※経済学だと、個人や企業などの経済を扱う「ミクロ経済学」と、もっと大きな規模の経済を扱う「マクロ経済学」というのがあるのですが、どちらかというと私は、かなり珍しい立場の「マクロ・スピリチュアリスト」的な文章ということになるのでしょうか?
まあ、そうした霊的な文章を載せても、霊的に大きな影響が及ぼせる場合と、ほとんどそうした影響がない場合もあるようなのですが、それでも現在の世界は、少しずつですが、昔とはかなり違った、より霊的な世界に移行してゆきつつあるので、そうした意味では、長い目で見ると、いろいろ良い影響もあるのではないか、と思って、そうした文章を載せています。
それから現在、あまり寒くなりすぎないように、もう少し暖かめの気が増えるように多少心掛けるようにしています。
また来年になったら、もう少し詳しく載せてゆきたいと思っているのですが、現在の世界は、以前よりも霊的な世界に変わってきているようなところがあるので、それぞれの人の思いや、あるいは、多くの人々の集団としての思いが、以前よりも、より早く現実の世界に何らかの形で現れてきやすくなってきているようなところがあります。
もちろん、そうしたそれぞれの人の思いや、多くの人々の集団としての思いのすべてがすべて、この世界に現れてくるわけではないし、また、そうした思いがあっても、できるだけ現実の出来事にならないようにした方がよいものも、たくさんあるとは思うのですが、しかし、それでも以前の時代と比べると、そうしたそれぞれの人の思いや、多くの人々の思いは、様々な形で現実の世界に現れてきやすくなってきているところがあるようです。
ですので2025年の現在の辺りの時代にも、そうしたこれまで、わりと隠れていることが多かった、それぞれの人の思いや、多くの人々の思いが、様々な形で現実の世界に現れてきたようなところがあったのではないか、と思われます。
しかし、それははっきり言って、すべての人が望むような良いことばかりではなかったようなところもあるので、そうした様々な出来事の中には、今後もたくさん起きてもよいような素晴らしい良い出来事もあれば、また、そうではなく、今後はできれば、もう二度と起きてほしくないような、とてもひどい大変な出来事も両方あったのではないか、というように感じております。
それゆえ現在は、霊的に見ると、多少大変な過渡期のような時期に当たっていると思うのですが、私は、それでももっと長い目で見れば、この世界は、だんだんとより良い世界に変わってゆくと考えているし、また、そうなる方向で、自分はずっと努力してゆきたいし、また、そうした良い世界になるように努力し続けている人々は、この世界には、たくさんいるのではないか、と強く感じております。
今年も、このブログを応援してくださった方々には、心から感謝しております。
また様々な形で、現在のアセンションに協力、応援してくださっている方々にも、心から感謝しております。どうもありがとう!
来年も、みなさんにとって、素晴らしい豊かな実りの多い一年となることを深く祈念いたします。
それでは、みなさん、来年も良いお年を!
Cecye
Cecye(セスィエ)
2025年12月31日 9:03 PM, おすすめ記事 / スピリチュアリズム、霊界 / 予知、予言、未来予測 / 人生観、世界観 / 時間と空間の秘密 / 現在のアセンションの状況 / 知恵、正しさ / 社会、文化 / 私の霊的な仕事について / 経済
それで「共産主義思想」についてなのですが、共産主義的な理想世界では、それまで、ずっと貧しい底辺の生活をしていた人々であっても、みんなで団結して、「資本家」と呼ばれるような、お金持ちや貴族や役人や軍人や知識人などを倒して、みんなで共同統治の平等社会にすれば、最高に素晴らしい理想社会ができる、というような思想として、捉えられていたように思われます。
しかし実際の共産主義思想は、後に多くの人々が批判しているようにそうした理想世界の提示自体はよいとしても、その思想の前提や理論や、実際の効果などに関しては、はっきり言って、それほど完成された、できのよいものではなかったわけです。
ですので、おそらく毛沢東自身も、実際にそうした共産党政権を作ってみると、若き日の彼が信じ込んでいた、あるいは信じ込まされていた理想とは、かなりかけ離れた政治や社会の状況になってしまうことが多かったので、後から、かなり困ったり、苦労したりすることが多くなっていたのではないか、と推測されます。
※彼はカリスマになっていないと、もう途中から政府が持たないような状況になっていたようなので、そうした彼個人の悩みや葛藤は、ほとんど表に出せないような状況になっていたのではないか、と思われます。
※先ほどから述べているように元々、毛沢東自身は、当時の中国の社会の状況を心から心配して、かなり理想主義的な理由から当時の共産主義思想にのめり込んでいったように思われます。しかし政治的、社会的には、その後、結構多くの人々が、共産主義や毛沢東に裏切られた、というか、結構、かなりひどい理不尽な人生を送らされた、というような状況になってしまったために、そうした人々の怒りや恨みの念によって、彼は霊的には死後、決して地獄というわけではないのですが、五次元以上の光の世界ではなく、もう少し暗い幽界的な領域に留まるような状況になってしまっているようです。
続く・・・
Cecye(セスィエ)
2025年12月29日 9:04 AM, 政治 / 知恵、正しさ / 社会、文化 / 経済
これは「霊的、歴史的な観点から見た現在の中国について」の続きの文章になるのですが、かなり長い文章になってきているので、ここからはタイトルを変更して、続きの文章を載せてゆきたいと思います。
3、霊的な観点から見た共産主義思想について
三つめは、これは、かなり難しい話になるかもしれないのですが、ここからは、それでは現代の中国では、政治や社会において、いったい、どこまでは共産主義思想を肯定して、また逆にいったい、どこからは共産主義思想をあまり全肯定せずに否定していった方がよいのか、ということについて、様々な観点から考えてゆきたいと思います。
中国において、共産主義思想を広めて、社会革命を起こして、共産主義政権を樹立したのは、現在の中華人民共和国の創設者の一人である「毛沢東」という人物になるのですが、はっきり言って、これはどこの国の歴史でも同じだと思うのですが、彼も、それ以前の古くからの中国の文化や中国の人々の生活習慣の中で様々な活動をしていたわけなので、あまりにも単純に現代的な価値観だけで、「毛沢東」という人物の活動の良し悪しを批判することは、この文章の主なテーマとは多少異なってきてしまうところがあるので、ここでは、いったん控えておきたいと思います。
私が思うには、おそらく若き日の毛沢東は、当時の中国の大変混乱した社会の状況において、「これなら中国の多くの人々を末長く幸福にできるような素晴らしい理想の社会にできるに違いない」というような強い信念をもって、当時の共産主義思想に飛びついて、そうした理想主義に基づいて、大変な革命や社会闘争にのめり込んでいったのではないか、というようには感じております。
ただ先ほども述べたように当時の中国は、それ以前からの中華民国の政府もあれば、当時のヨーロッパや大日本帝国などの勢力の支配に置かれている地域もあったし、また古くからの中国独特の生活感覚を持っている人々もたくさんいたような時代であったので、そうした社会において、毛沢東が理想とするような共産主義革命を行おうとしても、前にも述べたように、そもそも共産主義思想自体にも様々な問題があったわけなので、当時の毛沢東も、現代人的な感覚で言えば、本当はもっといろいろと穏便に上手にやりたかったことが、なかなかうまくいかずに大変な大混乱になってしまったり、かなり予期せぬ形で、たくさんの殺戮や闘争や奪い合いのような非常に大変な社会の状況になってしまうことも、結構たくさんあったのではないか、というように感じられます。
続く・・・
Cecye(セスィエ)
2025年12月29日 9:03 AM, おすすめ記事 / スピリチュアリズム、霊界 / 中国思想 / 人生観、世界観 / 宗教、道徳 / 政治 / 歴史 / 現在のアセンションの状況 / 知恵、正しさ / 社会、文化 / 経済
3、現在の辺りの時期は、一部の外国出身の人々の問題が多少大きくなり始めているようなので、日本人の社会として、どうしても許容できないものに関しては、ある程度きっちりと仕切り直しておく必要はあるだろう
ただ現在、一部の人々が強く危惧しているように、最近は一部の外国出身の人々が、かなりとんでもない犯罪や、反社会的な行為をするようになってきたり、どう見ても現在の日本人の社会では、とうてい受け入れることができないような危険な行為をすることも、だんだん増えてきているようです。
それゆえ私も、現在の辺りの時期にそうした日本人の社会として、どうしても受け入れがたい外国出身の人々の行為については、それなりに厳しい態度をとって、ある程度、きっちりと仕切り直しておいた方がよいのではないか、というようには感じております。
ただ、先ほども述べたように、一言で外国人と言っても、出身の国も違えば、それぞれの人の性格も生き方も、かなり大きく違うようなところがあるわけです。
ですので、確かに日本の社会として、「こうした行為は受け入れらない」という明確な線引きをすることは、とても大事であるとは思うのですが、しかし、だからと言って、ちゃんと真面目に一生懸命、日本の社会に溶け込もうと努力して、生活している外国出身の人々については、はっきり言って、中には、普通の日本人以上に優秀で、人格的にも素晴らしい人々もいるはずなので、きっちり区別して、そうした人々には、できるだけ、より良い日本での生活が送れるようにいろいろとサポートしてあげることは、とても大事なのではないか、というように感じております。
Cecye(セスィエ)
2025年12月16日 9:03 PM, 予知、予言、未来予測 / 人生観、世界観 / 政治 / 教育 / 知恵、正しさ / 社会、文化 / 経済
2、真面目に誠実に一生懸命努力している外国出身の人々については、きっちりと評価して、活躍の機会を与えたり、少しでも快適な生活がしやすくなるようにしっかりサポートしてゆくことは、とても大事である
二つめは、確かに一部の外国出身の人々には、大きな問題があるかもしれないけれども、しかし一見同じような外国出身の人々であっても、日本の法律や文化や習慣をしっかり尊重して、真面目に誠実に学業や仕事を一生懸命頑張りながら生活している外国出身の人々も大勢いるわけです。
それゆえ、そうした人々には、できるだけ日本人と同じようにきっちり評価して、活躍の機会を与えたり、また、そうした人々が、できるだけ快適に楽しく生活してゆけるようにしっかりサポートしてゆくことは、とても大事なのではないか、ということです。
つまり同じ外国人と一くくりにしてしまっても、なかには、日本の法律や文化や習慣をしっかり尊重して、本当に真面目に一生懸命、彼らにとっては異国の地である日本で勉強したり、仕事したりして、生活している人もたくさんいるわけです。
それから、なかには、本当に日本の文化や生活が大好きで、日本にやってきて、いろいろな体験をしながら生活している人々もいるようです。
ですので、そうした人々には、できるだけ日本の社会にうまく馴染んでゆけるように、いろいろなサポートをしてあげたり、また、そうした人々の希望ができるだけ、うまく叶うように手助けしていってあげることも、とても大事なのではないか、というように思われます。
続く・・・
Cecye(セスィエ)
2025年12月15日 9:03 PM, 人生観、世界観 / 政治 / 教育 / 知恵、正しさ / 社会、文化 / 経済
そうすると、たいていの人は、「政府が少子化対策に失敗したから、こうなったのだ」「現在の不景気の社会で子供を産み育てるのは、とても大変なので無理だ」などというような意見を言うことが多いのではないか、と思われます。
しかし現在の日本は、宗教や国家の教育などによって、結婚や出産、育児を奨励しているわけではないし、また、基本的に結婚や離婚、出産、育児などに関しては、それぞれの個人の自由に任されているようなところがあるので(基本的人権として保障されている)、はっきり言うと、これまでの日本の政治や社会の状況から推測すると、こうした問題をすべて政治の問題や責任にしていったとしても、今後も、なかなか、うまく解決してゆくことは難しいのではないか、というように私は感じております。
そうすると、もし現在のような社会の状況を大きく変えて、出生率を大きく増やしてゆきたいのであれば、政治的には、これまで以上に結婚や、出産や育児を強く奨励できるような、かなり大きな優遇策を打ち出したり、何らかの形で罰則のようなものを打ち出すだけでなく、企業や民間のグループや個人の活動など、社会全体としても、そうしたキャンペーンや、そうした人々を力強くサポートしてゆくような企画を出してゆかないと、一部の人々が、どんなに嫌がろうが反対しようが、現在の社会の状況を維持してゆくために、今後もどんどん外国出身の人々が、日本で働いたり、生活することは増え続けてゆくようになるのではないか、と思います(そうしないと今後も、そうした社会を維持してゆくために税金も社会保障費も、現在以上にどんどん上がってゆくのではないでしょうか?)。
※単純に言って、現在の日本の制度の場合、社会全体で見ると、同じ国民であっても、子供がいる人は、仮に年老いて、その人自身が働けなくなったとしても、その子供が成人して、働いたり、消費したり、税金や社会保障料を払ったりしていれば、その社会の維持には、ずっと貢献し続けていることになります。
ですので、現在の社会において、結婚して、子供を産み育てていたり、もう子育てを終わった人々が、「最近は一部の外国出身の人々が、ちょっととんでもない行動をしていて怖いので、なんとかしてほしい」と言っているのであれば、全く当然のことであると思うのですが、そうではなく、「自分は結婚はしたくないし、子供を産み育てる気もないが、外国人は気に入らないので、みんな出て行ってほしい」などと言っているのであれば、ちょっと考え方が違っているのではないか、というように思われます。
※これは一般論なので、様々な事情で結婚しなかったり、子供を産み育てられなかったような人を非難するような意図ではありません。そうではなく一部の人々の簡単に外国人を嫌悪したり、差別しようとする態度には非常に問題があるのではないか、ということです。
続く・・・
Cecye(セスィエ)
2025年12月10日 9:04 PM, 予知、予言、未来予測 / 人生観、世界観 / 政治 / 歴史 / 知恵、正しさ / 社会、文化 / 経済
最近は日本でも、外国人の問題がたびたび取り上げられることが多くなってきたようなので、今回は、そうしたことについて、少しだけ述べてみたいと思います。
歴史的には、古代の大昔から文明が栄えると、だんだん少子化が進んで、その国に元々いた人々の人口が減ると共に、周辺の国々から移住した外国の人々が増えてゆくような人口の変化が起きることが多かったようです。
それで最近は、日本でも一部の外国出身の人々が、これまでは、まずは起きなかったような、よくわからない、とんでもない騒動や事件を起こすことが、だんだん、かなり目立つようになってきているので、そうした外国出身の人々に対して、非常に強い嫌悪感を感じたり、非常に強い危機意識を持つ人々が、だんだん増えてきているようです。
私も現在の辺りの時期に、多少混乱が大きくなり始めている外国出身の人々の問題について、政府がある程度きっちりと仕切り直すことについては、基本的に賛成の立場になるのですが、ここでは現在、世間では、あまり触れられないことについて、幾つか述べてみたいと思います。
1、いくら外国人を嫌がっても、日本人の結婚や出産、育児を社会全体で、かなり強力に奨励し、サポートしてゆかない限り、今後も外国人は、どんどん増え続けてゆくことになるだろう
まず一つめは、みなさんもよくご存知のように現在の日本は、少子化が進んでいて、様々な産業で働く人々が根本的にかなり足りなくなってきているようなので、はっきり言うと、もう今現在の時点でも、外国出身の人々に数多く働いてもらわないと、その産業が維持できないような仕事が、たくさん増えてきているようなところがあります。
ですので根本的な問題としては、いくら一部の人々が、「外国出身の人々には、もう増えてほしくない」などと思ったとしても、現在のような形で日本の少子化がどんどん進んでゆく限りは、今後も日本では、外国出身の人々がたくさん働くような社会になってゆくのは、絶対に防げないような状況になってきているということです。
それゆえ、一部の人々の気分として、「もうこれ以上、外国人が増えないでほしい」と思うのはわからなくもないのですが、もし、そうした社会の問題を根本的に何とかしたいと思うのであれば、現在の日本で、結婚する人々の人数を増やすと共に(それから離婚するカップルを減らしてゆくことも、とても大事です)、出産や育児をして、子供を産み育てる家庭を増やしてゆくしかないのではないか、と思われます。
続く・・・
Cecye(セスィエ)
2025年12月10日 9:03 PM, おすすめ記事 / 予知、予言、未来予測 / 政治 / 知恵、正しさ / 社会、文化
それゆえ現在、世界的に経済は、かなり不安定な時代に入ってきているだけでなく、現在の中国も長期不況になってきているようなのですが、今述べたような、これまでの中国の歴史の経緯を見る限り、現在の中国が、共産主義的な国家運営を強めて、国民の引き締めや、欧米や日本などの自由主義の国々との対決姿勢を強めようとしすぎると、かつての中国のように経済的な大停滞時代に戻って、ここまでせっかく築き上げてきた国民の豊かさを大きく失うような事態に陥ってしまったり、さらにはそうした大変な社会状況の打開のために、かつての第日本帝国の末期のように国民の隅々に至るまでのかなり強力な国家統制や、欧米や日本などの自由主義の国々との軍事的な衝突に向かっていってしまう可能性もあるので、こうしたことには、非常に注意が必要なのではないか、ということです。
ですので、私も中国の政治や治安が大きく混乱するような状況になることは全く望んでいないのですが、もし中国が、現在の長期不況をきっちりと克服して、さらに豊かな国民の生活や国家の繁栄を目指してゆきたいのであれば、先ほどから何度も述べているように、共産主義のイデオロギーを表に出して、あまりにも大きく振りかざすような政治の手法はできるだけ控えて、現在、ともすれば冷え込みがちになっている欧米や日本などの自由主義の国々との、できるだけ協調的な国家のあり方を模索して、単に中国の人々や企業だけの利益を求めるのではなく、できるだけ相手の国も自分の国も双方がウインウインになって、一緒に繁栄してゆけるような外交や経済の関係を、少しでも確実にきっちり結ぶと共に、そうした自由主義の国々の法律や人権などについても、できるだけ、しっかりと尊重するような国家の姿勢を持つようにしてゆくことが、とても大事なのではないか、ということです。
「霊的な観点から見た共産主義思想について」の文章に続く・・・
Cecye(セスィエ)
2025年12月6日 10:03 AM, 予知、予言、未来予測 / 政治 / 歴史 / 知恵、正しさ / 社会、文化 / 経済 / 軍事
しかし実際には、現在までの中国の歴史を見ると、確かにかつて欧米や日本などの自由主義、または資本主義の国々の侵略や植民地支配に散々苦しんだことはあったかもしれないけれども、さらに少し歴史を遡れば、かつてはその中国も様々な国々に対して、たくさんの侵略や抑圧的な支配を行い続けてきた国だったのであり、また第二次世界大戦後、そうした中国が共産主義政権になった後も、たくさんの政治的な行き過ぎや失敗で多くの中国の人々の命を奪ったり、軍事的な侵略を行ったり、中国の多くの人々を、非常に長い経済的な停滞や貧困の中に起き続けてきた歴史の経緯もあったわけです。
そして現在の中国政府の立場としては、これまでの経済的な成長や、国の近代化の成果は、すべて中国の共産党政権の手柄にして、現在の長期不況や国内の問題の原因は、すべて一部の官僚や企業や国民の間違いや、外国の責任に押しつけてしまうような政治姿勢をとろうとするのは、先ほどから述べているような共産主義的な考え方や、中国を世界の中心と見るような中華思想から見たら、極々当然のことのように思われるようなところもあります。
しかし、よくよく冷静に現在までの中国の大きな発展の理由を、ある程度客観的な目で見直してみると、実際には第二次世界大戦後の共産主義に基づく中国の国家運営では、中国の政治的な統一には成功したもののその後、農業的に大失敗して、数千万の餓死者を出したり、軍事的な侵略を行うことになったり、ずっと経済的に停滞して、多くの人々が貧困状態に置かれたままになっていたような歴史の経緯もあったわけです。
ところがその後の中国は、主として70年代以降の改革開放政策によって、当時のソ連や社会主義の国々との協力関係を深めるのではなく、欧米や日本などの自由主義の国々に対して、国際的な外交関係や協力関係を深めていった結果、現在のような自由貿易体制の下、そうした欧米や日本などの自由主義の国々の政治や経済の仕組みを部分的に取り入れたり、それから、そうした国々からのかなりたくさんの経済援助や企業の進出や、技術支援などを受ける形で、様々な国々から資源やエネルギーを輸入したり、また、そうした欧米や日本などの自由主義の国々にたくさんの工業製品の輸出を行うことによって、大きく経済的に発展して、かなり豊かな国民生活を送れるようになってきたのではないか、ということなのです。
続く・・・
Cecye(セスィエ)
2025年12月4日 9:04 PM, 中国思想 / 政治 / 歴史 / 知恵、正しさ / 社会、文化 / 経済 / 軍事
ここまで様々な観点から欧米や日本などの自由主義の国々の状況と、特にここ最近の中国の状況について、述べてきたのですが、結局、ここでは何が言いたいのか、というと、だいたい次のようなことが言えます。
現在までの様々な状況から推測すると、どうも現在の中国の政府は、特にここ最近の中国国内の景気の冷え込みや、国民の生活への不満などに対して、様々な対策を打ったり、非常に神経を尖らせて、監視の目を光らせるだけでなく、できるだけ、そうした国民の不満を外国の責任に押しつけるために外国との対決姿勢をとろうとすることが多くなってきているようです。
また欧米や日本などの自由主義の国々は、できれば、少し前の時代のように、これまでとなるべく同じような形で中国との外交関係や経済協力を進めてゆきたいと思ってはいるのですが、その一方で、そうした欧米や日本などの自由主義の国々も、昨今の経済的な問題や国内の問題ばかりでなく、ここ最近の中国政府の欧米や日本などの国々への対決的な姿勢や、覇権主義的な軍事力の拡大や、自由や人権の蹂躙などの問題には、だんだん他人事ではなく、非常に身近に脅威や危険を感じるようになってきていて、少し昔の時代のように、そう気軽に活発には中国への経済的な投資や協力が、なかなかしづらい状況にだんだん変わってきているようなところがあるようです。
しかし、先ほどから述べているように中国の政府としては、現在までの中国の発展は、かつて欧米や日本などの国々から大変な侵略や植民地支配を受けて、散々苦しんだ中国の人々が共産主義思想の下、一致団結して、成し遂げた偉大な成果なのであり、また、それはかつての世界に冠たる偉大な中華帝国の復興でもあり、そして、やがては、かつての仇敵である欧米や日本などの自由主義の国々も、そうした偉大な中華帝国の傘下に入るようになるべきなのだ、などというような政治姿勢を持っているようにも見受けられます。
続く・・・
Cecye(セスィエ)
2025年12月4日 9:03 PM, 政治 / 歴史 / 知恵、正しさ / 社会、文化 / 経済 / 軍事