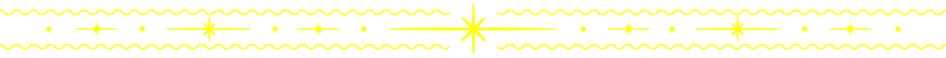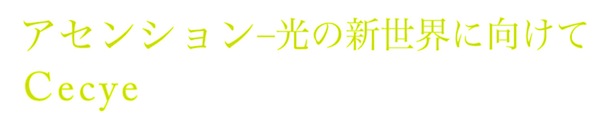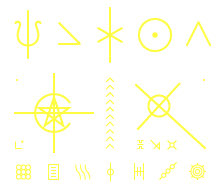世間はクリスマス一色ですが、昨年もこのブログでは、「クリスマス」と言っても、かなり変わった「イエス」の話を書いていましたが、今年も相変わらず、クリスマスとは、ほとんど関係ない「愛」の話の続きを、あと何回かに渡って、載せてゆきたいと思います。
2、宗教的、道徳的な「愛」のあり方と、この世的な「愛」のあり方が、真っ正面からぶつかった際には、決して安易に強硬的な態度をとらずに、神仏の意思は十分に尊重するにしても、できるだけ現代的な視点で多くの人々が、最も平和に幸福に繁栄できるような「愛の実現」を目指してゆくべきである
第二には、これは特に数百年の間、どの国や地域でも非常に問題になってきた内容になるのですが、要するに昔からの宗教や道徳で説かれてきた「愛」(もしくは慈悲)の内容と、それから特に近現代の民主主義や自由主義の勃興や、主として産業革命以降の物質的な豊かさの実現による、この物質社会における「愛」の内容が、いろいろな所でぶつかり合うことが多いために、いまだに現在の時点でも、「これが最も適切な愛の実現だ」とか、「これが人類の社会における最善の愛のあり方だ」というような最善の愛の形が、はっきりと見えないようなところがあるということなのです。
これははっきり言って、今後も、その時々のその国や地域の社会のあり方によって、「神」や「仏」というよりかは、そこにいる多くの人々が、自分達の意思で一つ一つ、しっかり責任をもって、決めてゆかなくてはならないような内容になってくると思われるのですが、これに関しては、現在の時点では、次のような三つのことが言えます。
まず第一には、とかくそうした宗教や道徳の立場と、現実の多くの人々の意見や考えが食い違いやすいのは、ともすれば宗教的な立場の人々が、「これは神の言葉だ!」とか、「これは絶対的な神の意思だ!」などと言って、多くの人々の現実の仕事や生活上の不便や不幸というものを無視して、一方的にいろいろなことを押し付けがちなところにあるのではないか、ということです。
これに関する私の考えは単純で、たとえ昔の時代に述べられた「神の言葉」のようなものがあったとしても、前にも述べたように時代や地域が異なれば、全然違う判断が下されるようなところもあるので、それゆえ現在のように多くの人々がある程度、教育水準も高く、自分達の意思でいろいろなことを決めたり、自分達の責任でいろいろなことを変更できるような時代には、そうした「神の言葉」と言われるものの具体的な一言(ひとこと)一言をそのまま鵜呑みにするのではなく、その中に含まれる神の意思、もしくは神の考えをよくよく汲みとることの方を優先して、現代であると昔と違って、自然環境との共生のような視点はとても大切になるのですが、それ以外には、できるだけ多くの人々の平和や幸福や繁栄が実現できるような方向で、その時々において、新たに判断し直してゆけばよいのではないか、ということです。
第二には、その際に多くの人々が、結構切実に悩み、困ってしまうのが、「昔からの宗教的な掟や決まり事のようなものを、いったい、どこまで忠実に守ればよいのか」ということになるのではないか、と思われるのですが、これに関する私の見解は単純で、たとえ、そうした昔からの掟や決まり事のようなものがあったとしても、現実に多くの人々が困ったり、苦しんだりしているのであれば、とにかく、それをできるだけ最短時間で、最も効果的に解決できるような合理的な考え方や行動をとるのが一番であるということと、ただ、そうした時にも万が一、何か変わったことや異常なことが起きた際には、いつでも考え方や行動の原点を見直せるように、多少慎重な態度を持つことがとても大切なのではないか、ということです。
つまり現代においても、時折、何らかの経済性や合理性に基づく判断をしたにも関わらず、しばらく経つと結局、何らかの大問題が発生してしまうことがあるのですが、そうした際によく調べてみると、どうも昔の人も似たような問題で散々悩んだ末に、何らかのヘンテコな決まりや習慣を作っていたようなケースもあるので、そうしたことにも多少注意や配慮が必要なこともあるということです。
第三には、これはあまり言われない話になるのですが、実は、よく考えてみると、とかく「神様、仏様」の視点が重視されがちな宗教も元をたどれば、何のことはない昔々、ある時代のある地域で説かれた、そこに住む人々を最も平安に幸福に豊かにしてゆくための、いわゆる「幸福教」のようなものだったのではないか、ということです。
ただし宗教の場合は、こうした「幸福教」と言っても、巷のこの世的な幸福論とは異なり、たいてい、この宇宙の創造主である神仏の視点や、死後や来世といった霊界の視点や、それから宇宙の法則や魂の進歩の視点などが多分に織り交ぜられた観点から、そうした幸福のあり方が説かれることが多いのですが、ただ、そうした霊的な視点を除けば、基本的には、たとえ、いかなる宗教の教えであっても、何らかの幸福論の延長線上の存在であったということなのです。
ですから、こうした観点から見ると、もし、この物質世界における現実のあり方と、霊的、あるいは、宗教的な考え方が真っ正面からぶつかって、なかなか折り合いがつかない場合には、宗教的な信仰や戒律や教義や、歴史や伝統よりも、そこは単純に「神仏」と言われる霊的な存在の意思は、ある程度はしっかり汲みつつも、現在の多くの人々の平和や幸福や繁栄の実現の方を断固として、しっかりと選び取ってゆくことがとても大切なのではないか、ということです。
Cecye(セスィエ)
2012年12月25日 9:04 PM, イスラム教 / インド思想、ヒンドゥー教 / キリスト教 / スピリチュアリズム、霊界 / ユダヤ教 / 中国思想 / 人生観、世界観 / 仏教 / 健康、医療 / 宗教、道徳 / 愛について / 成功論、繁栄論 / 政治 / 教育 / 歴史 / 知恵、正しさ / 社会、文化 / 神道 / 経済 / 自然、生命